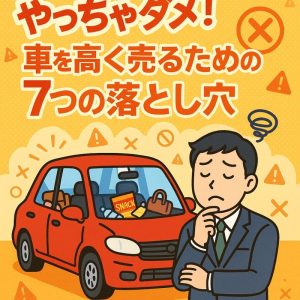えっ⁉️嘘みたいな車の雑学10選 Part3
(※Part1とPart2はこちら 👉 Part1 / Part2)
バイキングの好評シリーズの『えっ⁉️嘘みたいな車の雑学10選』の第3弾を書かせていただきました!
今回もアッと驚く嘘みたいな車に関する10個の雑学を書かせていただきました。
1. 夜でも“眩しくないライト”があるって本当?
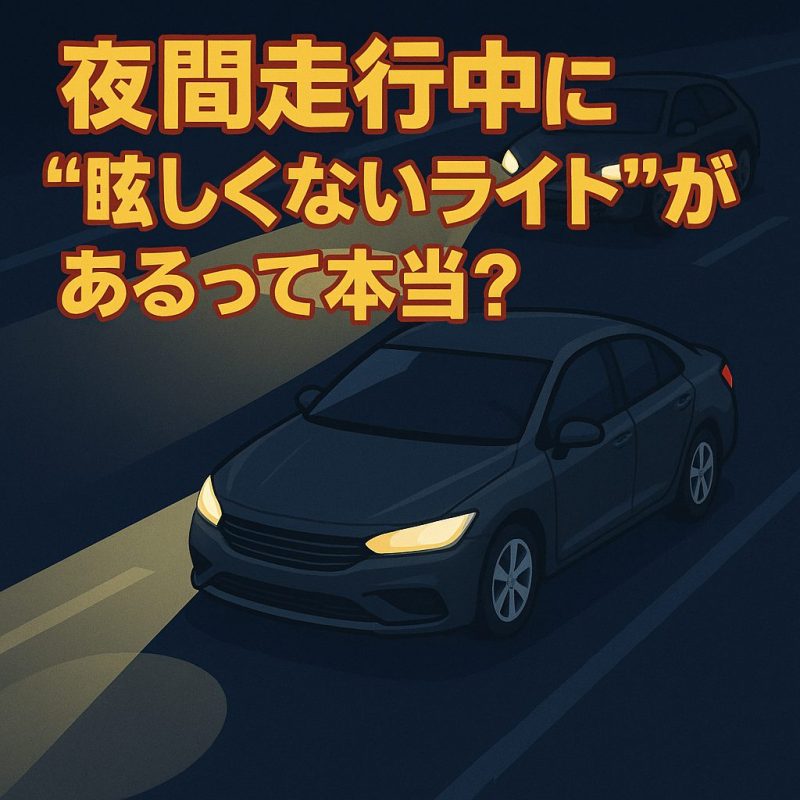
従来のハイビームは、対向車のドライバーを眩惑させるのが欠点でした。しかし最近の高級車では、赤外線センサーやカメラを使って相手の位置を正確に検知し、必要な部分だけ光を弱める「アダプティブハイビーム」が搭載されています。これにより、夜道でも安全に走行でき、しかも自動で最適な明るさをキープ。未来の話かと思いきや、すでに量産車に実装されている技術なんです。
2. パンクしても100km以上走れるタイヤ
「タイヤがパンク=すぐに交換」と思われがちですが、ランフラットタイヤは違います。サイドウォールを強化しているため、空気が抜けても50〜150kmは走行可能。雨の日や高速道路でのパンクでも、すぐに安全な場所まで移動できるのです。ただし耐久性が落ちたり、乗り心地が硬くなるデメリットもあるので注意が必要。いざという時の救世主的存在です。
3. 車の“顔”が売れ行きを左右する⁉️
自動車のフロントマスクは「顔」と呼ばれます。ヘッドライトは目、グリルは口。実際に人間が「優しそう」「怖そう」と感じるデザインは販売に直結します。例えば丸目のライトは親しみやすさを演出し、鋭いデザインは力強さや高級感を表現。メーカーが数ミリ単位でデザインを調整するのは、心理学的な効果を熟知しているからなのです。
4. 微生物で走る車の研究
バイオテクノロジーと自動車の融合は意外と古くからあります。微生物が持つ代謝エネルギーを利用し、電気を発生させる「バイオ燃料電池カー」の研究が進められてきました。まだメインの動力にはなりませんが、ライトやエアコンなどの補助電力として使う試みもあり、「地球と共生する車」という未来像を感じさせます。
5. ドアの角度で風切り音が変わる?
スポーツカーや高級車のドアラインには、実は空力的な工夫が隠されています。少し膨らませたり、角度を変えたりすることで、走行中に車体を流れる風をスムーズに導き、時速100kmを超えても風切り音を大幅に減少させられるのです。単なるデザインと思いきや、耳に優しい走行のための緻密な設計なのです。
6. 車内の“香り”が安全運転に繋がる
心理学の研究では、特定の香りがドライバーの集中力を高めることが分かっています。ラベンダーはリラックス効果、ミントは眠気防止に効果的。交通事故のリスクを減らす「香りによる安全対策」として、自動車メーカーが香りの演出を導入することも検討されています。芳香剤は単なるインテリアではなく、実は安全グッズでもあるのです。
7. 海底トンネルで車が凍る⁉️
青函トンネルやヨーロッパの海底トンネルでは、外気との差で発生した湿気が急激に冷え、車の窓やミラーに霜が付く現象が報告されています。走行中に視界がゼロになる恐ろしいケースもあり、トンネル管理者は通気や温度制御で安全を確保しているのです。普段は気にしない環境制御も、実は命を守る大切な仕組みです。
8. 世界一重いEVバスの発想
電気バスといえば軽量化が常識ですが、あえて“超重量級”にした試作車があります。重さによる安定感を活かし、慣性で長距離を走ることで省エネを実現。常識を逆手に取る発想で、都市交通の未来を切り拓こうとしているのです。
9. 電気自動車の“排気音”を選べる?
静かすぎるEVは歩行者に気づかれにくいため、安全のために擬似的な排気音をスピーカーで流しています。国によってはドライバーが好きな音を選べる仕組みもあり、クラシックカー風から未来的な音まで幅広いラインナップ。音までもカスタマイズする時代が来ているのです。
10. 変形して性能が変わる未来カー

「車高を下げて空気抵抗を減らす」「悪路では車体を持ち上げる」など、状況に応じて車の形を変えられるコンセプトカーが開発されています。まるでトランスフォーマーのようですが、実際にモード切替で走行特性が変わる仕組み。未来の車は“変形”が当たり前になるかもしれません。