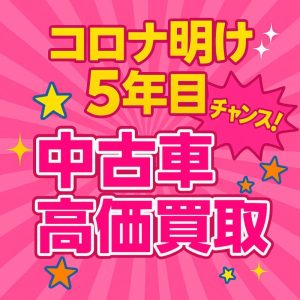お盆の帰省ラッシュ、実はこんな歴史があった!
お盆休み、実家への帰省を計画している方も多いのではないでしょうか?
毎年恒例の大渋滞。あのうんざりするような帰省ラッシュですが、実は高度経済成長期にできた習慣って知っていましたか?今回は、意外と知らない帰省ラッシュの歴史や豆知識をご紹介します。

帰省ラッシュはいつから始まった?
「お盆に実家に帰る」という習慣は、昔からあったわけではありません。
戦後、日本は高度経済成長期に突入し、多くの若者が地方から都会へと働きに出ました。故郷を離れて暮らす若者たちが、年に一度、お盆の時期に故郷へ戻るようになったのが、帰省ラッシュの始まりと言われています。
1960年代、新幹線や高速道路が整備され始めると、さらに帰省する人が増えました。車や鉄道の利用者が爆発的に増加し、現在のような大規模な交通渋滞が社会問題になり始めたのもこの頃です。
盆踊りの「盆」ってなんのこと?
お盆といえば「盆踊り」を思い浮かべる人も多いですよね。
この「盆」は、正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、サンスクリット語の「ウッランバーナ」が語源とされています。「逆さ吊りの苦しみ」という意味があり、お釈迦様の弟子が地獄で逆さ吊りにされている母親を救うために供養を行ったことが由来とされています。
盆踊りは、その供養のために集まった人々が踊ったことが起源と言われており、ご先祖様の霊を供養する意味合いが込められています。
帰省ラッシュ、昔と今の違いは?
昔の帰省ラッシュは、お盆の時期に一斉に帰省する人が多く、まさに「大移動」でした。しかし、最近では有給休暇が取りやすくなったこともあり、帰省の時期をずらす人も増えています。
交通手段も多様化し、飛行機やLCCを利用する人も増えたため、昔に比べると渋滞や混雑が分散される傾向にあります。
今年の帰省は、少し早めに出発したり、公共交通機関を賢く利用したりして、渋滞を避けて快適に過ごしたいものですね。
今年の夏も、安全運転で楽しいお盆休みを過ごしてください!